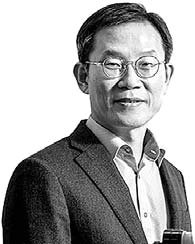李宗昊(イ・ジョンホ)ソウル大半導体共同研究所長(電気情報工学部教授)
--DRAM線間幅の縮小が限界に近づいたのでは。
「まだそうではない。線間幅を100ナノから10ナノ減らすのと、10ナノから1ナノ減らすのは、改善度が10%で全く同じだ。1ナノだからといって以前より改善速度が落ちたと見るのは適切でない。今でも以前と似た新製品開発周期を維持している。ただ、線間幅を減らすのがますます難しくなってはいるのは事実だ」
--NAND型フラッシュメモリーは何層まで可能か。
「わずか2、3年前までは100層超に疑問があった。ところがすでに100層を超えた。どこまで行けるか予断するのは難しい」
--NANDもDRAMもいつかは限界にぶつかるしかない。その後に対応してどんな準備をしているのか。
「いくつかの次世代メモリー候補を開発している。しかしまだDRAMの速度とNANDの価格・容量を上回るメモリーがない」
◆従来のメモリーに代わる新物質を探せず
基礎技術を研究しながら遠くまで眺めているためだろうか、学界は産業界より焦りを感じている。李宗昊(イ・ジョンホ)ソウル大半導体共同研究所長(電気情報工学部教授)は「今後の10年間にどうなるか分からない」と述べた。
--その間に追いつかれるということか。
「中国のDRAM技術も線間幅10ナノ台に入った。彼らは『韓国が8、9ナノまで行くことができるか』と考える。韓国が行き詰まった時に追いつくということだ。韓国は行くところがない。DRAMとNAND型フラッシュメモリーの次が見えない」
--対策は何か。
「その間、政府は『企業がよく頑張っている』としてメモリー研究開発(R&D)にほとんど投資してこなかった。研究費がないため教授も背を向ける。このため従来のメモリーに代わる新物質も見つけることができない。メモリーは韓国が主導権を逃せない分野だ。企業だけに任せることではない。集団知性が必要だ。長期的に眺めて政府がR&Dに注力しなければいけない」
--収率のような半導体生産技術では中国はまだ韓国に追いついていない。
「中国は人工知能が強い。人工知能を生産工程に取り入れれば短期間で収率を高める可能性もある」
【コラム】中国発メモリー危機論が浮上(1)
この記事を読んで…