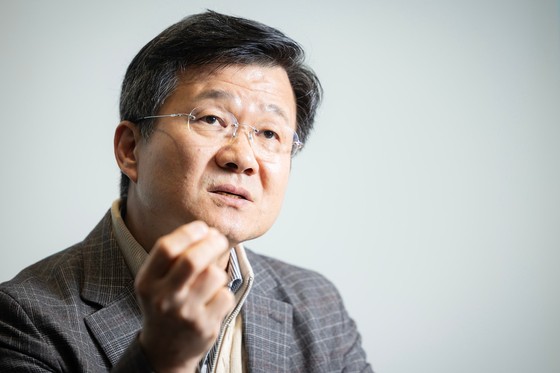3日、中央日報の社屋でインタビューに応じた姜恩瑚(カン・ウンホ)元防衛事業庁長 チョン・ミンギュ記者
--EUが再武装計画を発表した。ただ、「バイ・ヨーロピアン(欧州産購買)」方針のため、韓国防衛産業の接近は容易でないという見方もある。
欧州内でロシアに対して安保上の脅威を感じる程度に差がある。欧州の防衛産業先進国であるドイツとフランスは生産ラインを構築して自国の需要を満たすだけでも3-5年かかる見込んでいる。果たして気が短い東欧と北欧は待つことができるだろうか。この隙に食い込まなければいけない。昨年ノルウェーが韓国のK2戦車の代わりにドイツのレオパルト戦車を導入することにしたが、戦車の引き渡しまで数年かかる。我々はポーランドにK2戦車をわずか十数カ月で納品した。
これと関連しデンマークのメッテ・フレデリクセン首相は最近の記者会見で「国防相に伝えたメッセージはただ一つ、『(武器を)買って、買って、また買え』だった」とし「最上の武器を購買できなければ次善策を選択し、我々が望む武器の購買にあまりにも長い時間がかかるなら迅速に引き渡される別のものを選択しなければいけない」と強調した。
--今後3ー5年が機会ということか。
そうだ。米国に安保を依存してきた欧州国家がまた生産ラインを本格的に稼動するまでが我々には機会だ。防衛産業は基本的に政府対政府(G2G)事業だ。政府が総力支援をすべき理由がここにある。短くて3年、長くて5年後には機会の窓が閉まるかもしれない。我々が受注に成功すれば維持・補修と後続軍需支援などで今後20-30年が保障されるというのが防衛産業の特徴だ。うまくやれば韓国が3大防衛産業輸出国(G3)に入る可能性もある。
--機会を逃せばむしろ沈滞するおそれもある。
武器体系は絶えず性能改良をしなければならない。特に人工知能(AI)時代を迎え、従来の武器体系にAI搭載は必須だ。ここに入る莫大な投資金を確保するためにいま我々の武器体系を販売して稼いだ収益を積極的に活用しなければいけない。政府も防衛産業研究・開発(R&D)予算を本来の水準に早期に回復させ、未来の競争力を確保できるよう支援する必要がある。
--機会をつかむには何をするべきか。
庁長時代には相手国に現地生産を先制的に提案し、その部分をセールスポイントにした。50年の韓国防衛産業の経験とノウハウを共有するとアピールした。「防衛産業輸出」でなく「防衛産業協力」だと強調した。一部では「現地生産をすれば我々の技術が流出する」と批判する声があるが、核心技術20%だけを統制すればよい。現地生産すれば購買国の立場では技術移転と雇用創出、安定した供給が可能になる。我々の立場でも利点が多い。国内生産ライン増設による過剰・重複投資リスクを減らすことができる。「経路依存性」という言葉がある。我々の武器体系の生産ラインまで備えた国が他国の武器購買に転換するのは容易でない。韓国とは異なる気候環境、購買国の軍人の実際の運用パターンなどに合わせて政府と企業、運用ノウハウを持つ軍がワンチームとなり、後続支援を徹底すると約束しなければいけない。
シンクタンクのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2020ー24年に欧州内の北大西洋条約機構(NATO)加盟国が輸入した武器の64%が米国産と集計された。続いてフランスと韓国が6.5%、ドイツが4.7%、イスラエルが3.9%の順だった。
--欧州内で米国武器への依存度を低めるべきだという声が出ている。
米国と韓国の武器体系がカバーする領域は異なる。米国は高価な最先端武器体系に集中しているが、韓国は性能と価格競争力に強みがある。例えばウクライナ戦争で「ゲームチェンジャー」に浮上した米国の高機動ロケット砲システム(HIMARS)と我々の多連装ロケット「チョンム」は領域が重なるが、チョンムの価格は半分もならない。トランプ政権が欧州に米国産武器購買圧力を加える可能性も排除できないが、韓国防衛産業の欧州内シェアを高めることができる絶好の機会だ」
--米国が艦艇維持・補修・整備(MRO)協力を要請しているが。
米国は中国との覇権競争で最も重要な海軍力を構築する造船業の基盤が脆弱だ。ドック施設と専門技能労働力が絶対的に不足している。一方、中国は世界造船1、2位を争う状況だ。中国の艦艇はほとんどが過去10年間に建造されたが、インド太平洋司令部所属の米国の艦艇はほとんどが建造から20年以上経過している。ハンファオーシャンが最近、国内で初めて受注した米海軍軍需支援艦「ウォリー・シラー」のMRO事業を終えたが、米国側から好評を受けた。米国の艦艇に慣れている韓国造船会社は当面の問題だけでなく、近いうちに発生する問題まで把握できる技術力量と迅速な解決能力を備えているという点が立証された。
この記事を読んで…