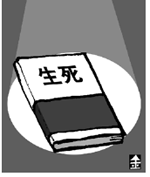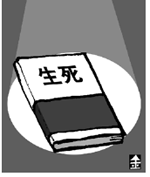 |
|
一人の女優の自殺が世間を驚愕させた。 これまで数人の芸能人が自ら命を絶ったが、今回は程度が違う。 20余年間、身内のように親しみが感じさせてきた大衆スターだった。 1990年代以降から飛躍的に成長した韓国演芸産業の象徴的な存在でもあった。 チェ・ジンシルはCMだけで浮上した「CMスター」1号だ。 ‘歩く中小企業’という呼称も初めてついた。 大衆スターの商品性を雄弁した最初のケースだった。 体系的なマネジメント時代を開いたりもした。
何よりも脱神秘スターだった。 今では誰もが気さくな姿を見せるが、当時はまだ芸能人は優越的な存在だった。 半面、チェ・ジンシルは貧しい幼児期を公開し、近所の人のような親近感で愛された。 彼女の日常的で溌剌とした魅力は、‘巨大談論’が消えた90年代の新世代文化トレンドとうまく重なった。 若い世代の恋愛風俗図を軽快に描くトレンディードラマが彼女を主人公とし、一気に発火した。 しっかりしたキャンディーのイメージで愛された彼女が、スランプの後、強いアジュンマ(おばさん)や‘ジュンマレラ’(アジュンマ+シンデレラの合成語)のイメージで再起したのも彼女らしい。
そういう彼女であっただけに、自殺が与える衝撃ははるかに大きい。 自殺ドミノを憂慮する視線も多い。 実際、韓国は経済協力開発機構(OECD)国家のうち自殺率が最も高い。 社会的競争が激しくなっているのが最も大きな理由だ。 自殺を死に対する自己決定権だとして「自殺権」を主張するジャン・アメリーのような人もいるが、自殺率が高い社会が幸せな社会でないのは自明だ。
『自殺、世の中で最も不幸な死』を書いた呉進鐸(オ・ジンタク)教授は「生死学」(Thanatology)という話を投じている。 自殺予防を越えて、生と死を新たに見る省察的な生死観を強調する。 よく自殺者は死ねばすべてが終わると考えるが、これは死に対する無知と誤解だと指摘している。 呉教授は「死を肉身の死でなく肉身と霊魂の分離と考えれば、また自身の存在を生と死をたどる霊魂の旅行と考えれば、生というものは放棄できない霊魂の成熟過程だ」とし「自殺に追い込む物神主義も死に対する誤った理解から始まった」としている。 ‘自殺衝動’が伝染病のように広がる時代、‘霊性’という解決法を投じたのだ。
この記事を読んで…